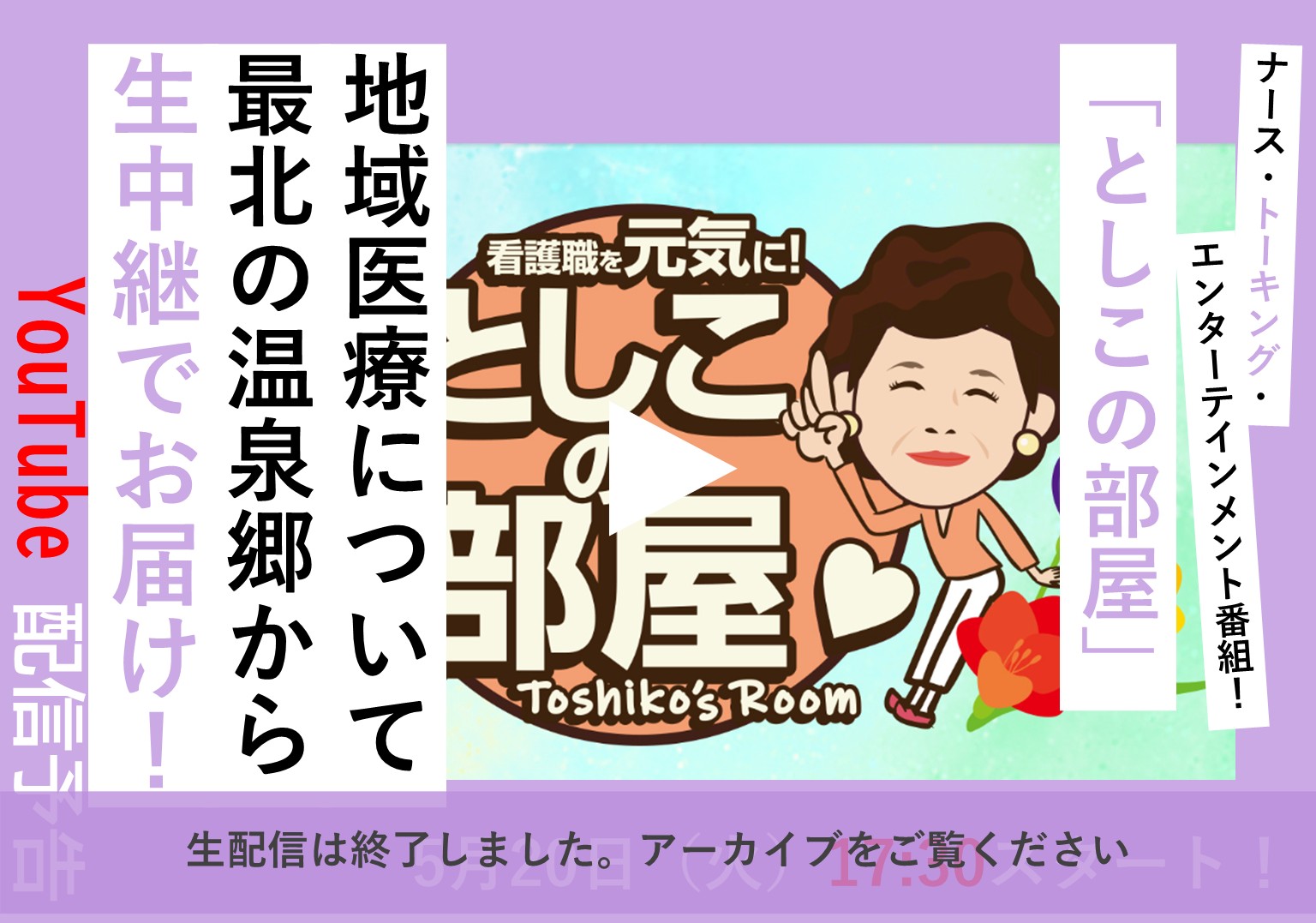病院などの医療施設で勤務し、病気の子どもたちのために精神的なケアや治療のサポートをする“ファシリティドッグ”をご存じでしょうか? 検査や処置、リハビリなどに付き添うことができ、病気の子どもたちの心の支えとなる存在です。今回ご紹介するのは、ファシリティドッグと二人三脚で子どもたちやその家族をサポートするハンドラーの資格。看護師として経験を積んだあと、日本初のハンドラーとして活躍する森田優子さんに、資格を取得した経緯と活動に込めた思いをお聞きしました。
資格のチカラ
2025/8
ファシリティドッグ・ハンドラー
ホスピタル・ファシリティドッグ®︎(以下、ファシリティドッグ)は、医療スタッフの一員として病院に常勤し、継続的に患者である子どもたちやその家族を支える、専門的な訓練を積んだ犬のこと。ファシリティドッグとペアを組んでサポート役を担うのがファシリティドッグ・ハンドラー(以下、ハンドラー)です。臨床経験をもつ医療従事者であることが必要で、多職種と協働して患者さんに合わせた治療的目標を計画・実行します。
病気の子どもたちの心を支える ファシリティドッグ・ハンドラーが担う新しい看護の形

資格取得年月(講師認定):2009年11月
看護師/ファシリティドッグ・ハンドラー
INDEX
ファシリティドッグの活動が広がったきっかけ
ハンドラーの活動内容
看護の仕事に対する変化とは
森田さんの今後の展望
ハンドラーを目指す人へ
病気の子どもたちの声で、ファシリティドッグと毎日会えるように
森田さんがハンドラーになられた時は、まだ日本でのファシリティドッグの認知度も少なかったんですよね。
今でこそ動物介在療法の認知度が高まりましたが、当時は犬が病院に入ること自体、本当に珍しいことでした。あったとしても月に数回や数カ月に一回、患者さんを癒すことが目的のセラピードッグとして導入されるのみ。ファシリティドッグの本来の役割である治療のサポートとして病院に入ることはできなかったんですよね。そのため私とベイリーも、まずは病棟の外の面談室にいて、ベイリーに会いたい子は保護者と一緒に会いに来てください、という形で活動をスタートしました。頻度も最初は週3日程度でした。
現在はファシリティドッグが毎日常駐していますが、何かきっかけがあったのでしょうか。
子どもたちが声を挙げてくれたことが一番大きかったですね。「なんで私のいる病棟にはベイリーが来てくれないんですか?」って。具体的には、小児がんなど薬によって免疫が落ちている子どもたちが多い病棟に、最初は入ることができませんでした。ですが、子どもたちやご家族の声によって病棟のプレイルームまで許可が下り、病室に入ってよいことになり、ベッドで添い寝もできるようになり、骨髄穿刺の検査など清潔を保たなければならない場面にも付き添えるように。段階を踏んで活動の範囲が広がっていきました。
週3日だけの導入から毎日になったきっかけも、子どもたちが院長室に乗り込んで、院長先生にかけ合ってくれたおかげなんです(笑)。当時、院長先生は「子どもたちはベイリーに毎日会いたいとは思っていない」と考えていたようです。ですが、とある子が院長先生に「ベイリーの必要性は健康な人にはわからないんだよ」と言ったことをきっかけに、考え直してくださったようで。後日講堂に職員を集め、院長先生から「来月からベイリーに毎日来てもらいます」と発表があった時、その場にいた看護師さんやスタッフの皆さんから拍手が起きたのを今でも覚えています。
 治療中の子どもに寄り添うアニーと森田さん
治療中の子どもに寄り添うアニーと森田さん
看護師の立場と患者さんの気持ち、どちらも理解できる存在に
現在のハンドラーとしての活動内容を教えてください。
ファシリティドッグとともに患者さんの病室を訪れ、触れ合うことが基本的な活動となります。患者さんもさまざまな症状の方がいらっしゃるので、看護師の知識や研修で学んだ内容を生かしながら、安全管理や感染管理に徹底して触れ合うようにしています。日々の触れ合いを通し、患者さんとファシリティドッグの“絆”をつくったうえで、さまざまな処置への付き添いも行います。いつも一緒にいてくれる犬がそばで応援してくれることで、患者さんもがんばって処置に望むことができるんです。具体的には、点滴や採血、検査、リハビリ、オペ室に入るまでの付き添いなどですね。どこまで付き添うかに関しては病院の考え方や希望もありますので、病院と確認しながら行っています。
あとは、スケジュール調整もハンドラーの大切な仕事です。私が現在活動している神奈川県立こども医療センターは430床ありますが、ファシリティドッグはアニー1頭のみです。犬は人間のように1日8時間働けるわけでなく、実質3時間くらいがマックスです。そのため、1日に会える子どもたちの数は平均10人程度。限られた時間の中ですので、プレイルームで元気に遊んでいる子よりは、病室で動けずにいる子の方になるべく時間を割くようにしています。他にも、術後の子どもが離床を促す時期だとわかれば、散歩に誘ってみたりとか。ベッドの上でリハビリを行うために、今必要な動きは何かなと考えたり……。看護師としてカルテを見ることができるので、患者さんの病状や処置や検査の予定などの情報を確認しながら、細やかにスケジュールを立てています。
ハンドラーとして働くうえで、看護の仕事に対する向き合い方に変化はありましたか?
患者さんと向き合う時の“目線”が変わったことですね。看護師として働いていた当時は、医療者目線になっていたなと。例えば、短時間で終わる小さな手術をする子を涙しながら見送る親御さんの姿を見ても、心から寄り添うことができなかったんです。もっと大きな手術はたくさんあるのになって……。ですが、ハンドラーとして、子どもたちへの寄り添いを目的に医療現場に入るようになったことで、子どもの小さな変化を心配する親御さんの気持ちを理解できるようになったと実感しています。
ファシリティドッグと一緒にニコニコしながら手術室に向かう子どもの姿を見るだけで、親としてはとても安心できるだろうなと思います。子どもたちが薬を飲む時や点滴をする時に、「アニーが一緒にいてくれるからがんばろう」と思う力を引き出せるのは、やっぱりファシリティドッグだからこそできること。そんなファシリティドッグと一緒にサポートできる今の活動を誇りに思っています。
 「ベイリーやアニーと暮らすようになり、彼らがちょっとお腹を壊しただけでとても心配になる自分がいます。そうした変化からも、子どもを想うご家族への理解が深まったように思います」
「ベイリーやアニーと暮らすようになり、彼らがちょっとお腹を壊しただけでとても心配になる自分がいます。そうした変化からも、子どもを想うご家族への理解が深まったように思います」
看護師としての経験の延長線上に、ハンドラーの活動がある
森田さんの今後の展望を教えてください。
私自身は今年の4月からマネジメントに移行しています。ここ1~2年でファシリティドッグの需要も高まっていて、現在4組で活動しているファシリティドッグチームも数年以内には10組以上誕生する予定です。
当法人は国内4病院と協働で15年間活動を続けてきて、ノウハウも蓄積しています。内部でも医療安全係や感染対策係を設けたり、勉強会の実施や全体会議での情報共有の場をつくったりもしています。また、医師や獣医師、国内外の使役犬事情に詳しい専門家などに「アドバイザリーボード」として入ってもらい、アドバイスや活動のチェックも受けています。ファシリティドッグの活動は、こうした取り組みにより医療機関で安全に行うことができるのです。
近年、動物介在療法に関心を寄せる医療機関が増えていますが、おとなしい犬と看護師がいればファシリティドッグとして活動できるわけではありません。正しい医療安全の知識と、不測の事態にも備えられる体制のもとで活動し、病院と協働した対策を講じるからこそ、病院側からの信頼を得ることができると確信しています。これからも安全に活動を続け、かつ日本の医療機関に持続可能なファシリティドッグ導入を広めていくためにも、日本の第一人者として啓発活動を進め、医療従事者の理解促進を図る必要性を感じています。適切な情報発信を行い、ファシリティドッグの取り組みを正しく社会全体に広めることが、今の私の展望ですね。
最後に、これからハンドラーを目指す方に向けてアドバイスをお願いします。
今ではファシリティドッグや動物介在療法の認知度が高まり、活動に携わりたいと考えている看護師さんや医療従事者が増えてきています。とてもうれしい反面、私自身が活動を通して思うのは、看護師としての経験の延長線上にハンドラーとしての活動があるということです。看護の現場で培ってきた経験や看護観をもち得ているからこそ、患者さんやそのご家族と同じ目線に立ち、サポートができる仕事だと実感しています。
なので、まずは看護師としての経験をしっかり積むことが大切。その経験が必ずハンドラーとしての活動に生きてくるはずです。

写真:戸井田 夏子

“What’s in my bag?” アニーとの活動時に欠かせないグッズとは?

「活動の時はアニーに必要なグッズを常にもち歩いています」と話す森田さんのカバンの中身を拝見。(写真左上から時計回りに)ベッドに付いた毛を取るコロコロ、手やおもちゃを拭く除菌シート、リード、床やベッドに座る時に使うシート、顔拭き、アニーの名刺、音が鳴るおもちゃとボール、折り畳みの水入れ、名札を見せていただきました!
取得方法・お問い合わせ
| 資格主催団体名: | 認定 特定非営利活動法人 シャイン・オン・キッズ |
|---|---|
| 資格種類 | ファシリティドッグ・ハンドラー |
| 研修受講資格 | 5年以上臨床経験をもつ、看護師をはじめとする医療従事者 その他、資格取得方法の詳細はこちらをご覧ください。 |
| ホームページ: | https://sokids.org/ja/ |
SNSでシェアする