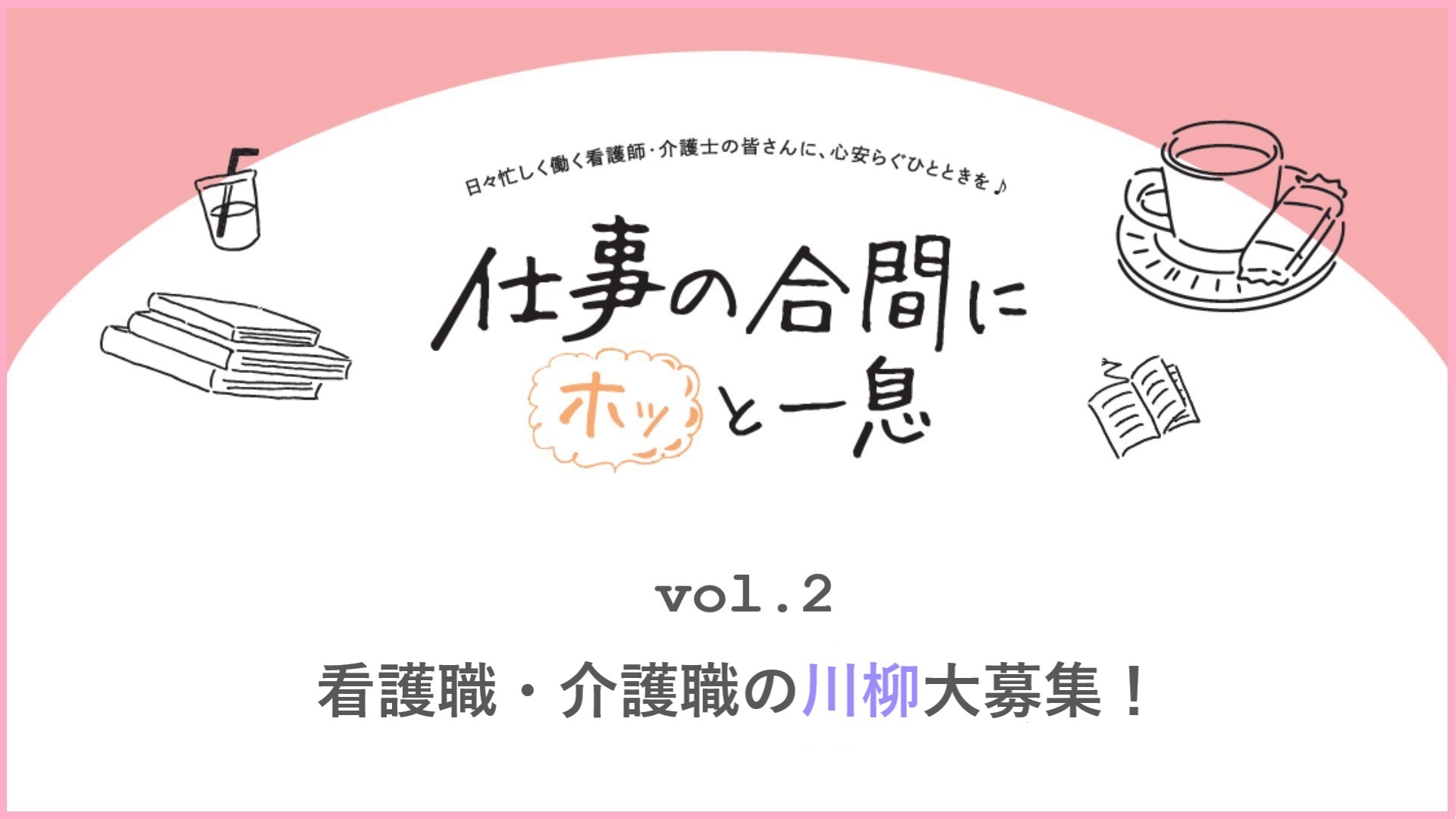認定介護福祉士は、介護の現場で培ってきた経験と知識を生かし、ご利用者や職場、地域などと広く関わりながら支援する使命を担っています。介護福祉士の上位資格ながら知名度がまだまだ不足していることや、600時間に及ぶ研修が必要である厳しさもあり、登録者はわずか100名程度(2022年時点)。それでも多くの介護福祉士がキャリアアップを目指し、難しい条件をクリアしようと努力しています。介護施設を運営するかたわら、認定介護福祉士の資格を取得した田中栄さんに、資格取得の経緯、資格を生かした活動についてお話をうかがいました。
資格のチカラ
2022/12
認定介護福祉士
認定介護福祉士は、介護福祉士の上位資格として2015年12月から認証・認定を開始した民間資格です。居宅・施設系サービスを問わず、多様なご利用者、生活環境、サービス提供形態に対応し、より質の高い介護実践や介護サービスマネジメント、介護と医療の連携強化、地域包括ケア等を行うスペシャリストとして、注目度が高まっています。
全国にわずか100名! 介護職の最上位資格・認定介護福祉士への挑戦

株式会社フォレスト 代表取締役
群馬県介護福祉士会 常任理事
資格取得年月:2022年10月
介護福祉士・介護支援専門員・准看護師
研修を受けて知った学びの楽しさ
認定介護福祉士は、2015年にできたばかりの新しい資格です。田中さんがこの資格を取ろうと思ったきっかけは?
私は2003年に介護サービスの会社を起業し、無我夢中で仕事をしてきました。それから10年以上経ち、介護福祉士の専門性を担保するために、日本介護福祉士会が生涯研修を推進していることを初めて知ったのです。当時の私は、本業も落ち着いてきて時間に余裕ができたタイミングでしたし、「私も勉強してみようかな」と思い始めました。そんな軽い気持ちで、群馬県介護福祉士会で開催している生涯研修のひとつであるファーストステップ研修を受けたのが最初のきっかけです。すべての講義が刺激的で、 その頃日本介護福祉士会のホームページで認定介護福祉士資格を知りました。「介護について発信する人になりたい」という夢を叶えるためにも、認定介護福祉士へのキャリアアップを目指そうと思いました。
認定介護福祉士になるには、600時間もの認定介護福祉士養成研修を受講する必要があります。実務との両立は、大変だったのでは?
私は施設の代表なので、ある程度スタッフに仕事を任せることができます。そのため、時間の融通は利きました。とはいえ、私が暮らす群馬では研修を受けられず、近隣の長野もすでに定員オーバー。そのため、研修のために月に2、3回群馬から静岡に通うことになりましたし、途中でコロナ禍になり、本来は3年で修了するはずが4年かかることに。JR東日本の「大人の休日倶楽部」に入って交通費を節約したり、電車の中では電子書籍の端末で参考書を読んだりしながら、お金と時間をやりくりしました。

認定介護養成研修で、特におもしろかったのはどんな内容でしたか?
研修の内容はもちろんですが、根拠を示すためにデータを引用したり、それを分析して考察したりといった学術研究の手法に興味を抱きました。私は高校卒業後すぐに医療の業界に飛び込んだため、大学教授から直接教えを受けられるのもとてもうれしかったです。学ぶ楽しさを知ったため、私が経営する施設の職員についても「研修を受けたい」という希望があれば、どんどんバックアップするようになりました。
次のページ:現場実践が1冊の本に

移動中は電子書籍の端末を活用して読書
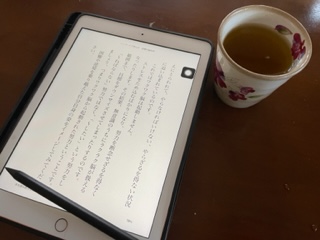
「時間や場所を問わず読書できるよう、本はKindleで購入しています。講師が講義中に勧めてくれた本、文章作成のハウツー本、ファシリテーション力を身につけるための本など、興味のある書籍を次々に読んでいます」(田中さん)
◆田中さんのおすすめ本◆
・『ハーバードで学んだ 逆境の脳科学』著:川崎 康彦 出版:青春出版社
・『成果を生み出す思考習慣』 著: 坂本 健 出版:Next Publishing Authors Press
・『論文・レポートの基本』 著:石黒 圭 出版:日本実業出版社
取得方法・お問い合わせ
| 資格主催団体名: | 一般社団法人 認定介護福祉士認証・認定機構 |
|---|---|
| 資格種類: | 一般社団法人 認定介護福祉士認証・認定機構 民間資格 |
| 受講要件: | 次の1~4の項目をすべて満たしたうえで、認定介護福祉士養成研修を受講し、全科目(22科目)を修了(単位取得)する必要がある。 1. 介護福祉士の資格を有していること。 2. 介護福祉士資格取得後の実務経験5年以上。 3. 介護職員を対象とした現任研修の100時間以上の研修歴を有していること。 4. 研修実施団体の課すレポート課題または受講試験において一定の水準の成績を修めていること(免除の場合有)。 |
| ホームページ: | 認定介護福祉士認証・認定機構 認定介護福祉士になるには |
SNSでシェアする